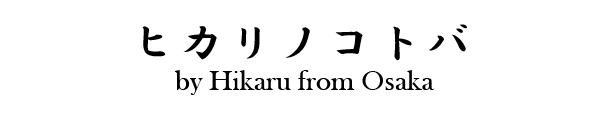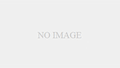古市駅に降り立つと、冬の夕方特有の澄んだ空気が、胸の奥までスッと入り込んできた。ホームに残るわずかな人影と、遠くで聞こえる電車のモーター音。そのどれもが、この街の時間の流れがゆっくりであることを教えてくれる。
改札を出ると、ほのかに土の匂いを含んだ風が吹いた。
「今日は歩いてみるか」
そんな気分の日だった。
駅前の通りを抜けると、古市の景色はすぐに“現代”から“昔”へと表情を変えていく。民家の屋根瓦、古い石垣、そして時折あらわれる細い路地。それらが、まるで「ここには長い長い物語があるんだ」と語りかけてくるようだった。
白鳥神社へ向かう道のりは、ただの散歩道ではない。
古代から人々が往来してきた土地であり、時代ごとの風が積み重なっている場所だ。
歩くにつれ、足音だけが静かに響き、心がゆっくりと落ち着いていくのがわかった。
――人は歴史のある場所に来ると、自然と呼吸が深くなる。
そんな気がする。
やがて、木々の隙間から白鳥神社の鳥居が見えてきた。
あの赤い鳥居が、冬の柔らかい光の中で静かに立っている。
鳥居の前に立つと、空気が一段と澄んだものに変わる。
「ただいま」と言いたくなるような、不思議な安心感があった。
鳥居をくぐり、参道へ足を踏み入れた瞬間、周囲の音がふっと小さくなった。まるで、境内全体が“静けさという名の結界”を張っているかのようだ。
左手には苔むした石灯籠。
右手には、冬でもしっかりと葉を茂らせた木々。
その間を抜けるとき、古代から続く“見えない気配”が肩に乗ってくる気がした。
「ここは、昔から人が祈ってきた場所なんだな」
本殿の前に立つと、思わず背筋が伸びた。
手を合わせると、風がふわりと頬を撫でた。
ただそれだけのことなのに、心の中のざわつきがひとつずつ静まっていく。
祈りが終わり、境内を少し歩く。
小さな社、古びた案内板、手水舎に落ちる水の音。
どれもが、“人の時間”と“神の時間”がゆっくりと混ざり合いながら流れているようだった。
帰り道、振り返ると鳥居越しに見える空は、わずかに赤みを帯びていた。
一日が暮れていくその瞬間、ふと気づく。
「歴史は、本の中ではなく、こういう場所の空気に残っているんだ」と。
古市駅までの道のりを歩きながら、胸の中に温かいものが灯っているのを感じた。
何か特別な出来事があったわけではない。
白鳥神社に足を運んだだけだ。
しかし、人はときどき、こういう“ゆっくりした時間”に救われることがある。
古市の街と、白鳥神社の静けさが、そんな時間をくれたのだった。